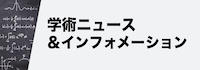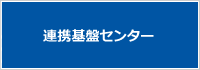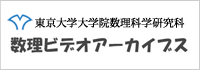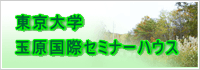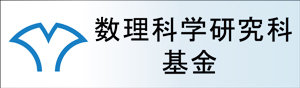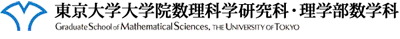情報数学セミナー
過去の記録 ~02/27|次回の予定|今後の予定 02/28~
| 開催情報 | 木曜日 16:50~18:35 数理科学研究科棟(駒場) 118号室 |
|---|---|
| 担当者 | 桂 利行 |
過去の記録
2024年02月08日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
菅野 恵太 氏 (株式会社QunaSys)
量子コンピュータとその応用の現状 (Japanese)
菅野 恵太 氏 (株式会社QunaSys)
量子コンピュータとその応用の現状 (Japanese)
[ 講演概要 ]
量子コンピュータは近年急速な発達を遂げている一方、未だ本格的な産業応用には至っていない。本講演では、量子コンピュータ開発の現状と展望を、産業応用を目指して量子アルゴリズム研究開発を行うベンチャー企業の視点から紹介する。
量子コンピュータは近年急速な発達を遂げている一方、未だ本格的な産業応用には至っていない。本講演では、量子コンピュータ開発の現状と展望を、産業応用を目指して量子アルゴリズム研究開発を行うベンチャー企業の視点から紹介する。
2024年01月25日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 056号室
鈴木 泰成 氏 (NTT)
誤り耐性量子計算機の設計と制御 (Japanese)
鈴木 泰成 氏 (NTT)
誤り耐性量子計算機の設計と制御 (Japanese)
[ 講演概要 ]
高速な量子計算を実現するには、量子誤り訂正符号を用いた誤り耐性量子計算機の実現が重要となる。この講演では符号化された量子情報に対する基本演算や、量子アルゴリズムを基本演算に翻訳する方法について解説する。
(講義は056号室で行われます。)
高速な量子計算を実現するには、量子誤り訂正符号を用いた誤り耐性量子計算機の実現が重要となる。この講演では符号化された量子情報に対する基本演算や、量子アルゴリズムを基本演算に翻訳する方法について解説する。
(講義は056号室で行われます。)
2024年01月11日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
鈴木 泰成 氏 (NTT)
量子計算と量子誤り訂正の基礎 (Japanese)
鈴木 泰成 氏 (NTT)
量子計算と量子誤り訂正の基礎 (Japanese)
[ 講演概要 ]
高速な量子計算を実現するには、量子誤り訂正符号を用いた誤り耐性量子計算機の実現が重要となる。この講演では量子情報と量子誤り訂正符号の基本的な枠組みについて説明する。
高速な量子計算を実現するには、量子誤り訂正符号を用いた誤り耐性量子計算機の実現が重要となる。この講演では量子情報と量子誤り訂正符号の基本的な枠組みについて説明する。
2023年12月21日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
山川 高志 氏 (NTT)
量子計算と暗号 (Japanese)
山川 高志 氏 (NTT)
量子計算と暗号 (Japanese)
[ 講演概要 ]
量子計算と暗号理論の関わりについていくつかのトピック、具体的には量子マネーや暗号を用いた量子計算機の検証等について解説する。
量子計算と暗号理論の関わりについていくつかのトピック、具体的には量子マネーや暗号を用いた量子計算機の検証等について解説する。
2023年12月14日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
富田 潤一 氏 (NTT)
関数型暗号と属性ベース暗号 (Japanese)
富田 潤一 氏 (NTT)
関数型暗号と属性ベース暗号 (Japanese)
[ 講演概要 ]
関数型暗号は、暗号化されたデータから元データの関数値だけを復号することが可能な暗号である。この講演では関数型暗号とその重要な下位概念の一つである属性ベース暗号について、基本的な内容から最近の研究の進展についてまでを概説する。
関数型暗号は、暗号化されたデータから元データの関数値だけを復号することが可能な暗号である。この講演では関数型暗号とその重要な下位概念の一つである属性ベース暗号について、基本的な内容から最近の研究の進展についてまでを概説する。
2023年12月07日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
西巻 陵 氏 (NTT)
暗号学的プログラム難読化とその応用 (Japanese)
西巻 陵 氏 (NTT)
暗号学的プログラム難読化とその応用 (Japanese)
[ 講演概要 ]
暗号学的な意味で安全なプログラム難読化とは何かを説明し、その実現方法や応用について解説する。特に実現方法において重要な関数型暗号や暗号学的多重線形写像との関わりについても解説する。
暗号学的な意味で安全なプログラム難読化とは何かを説明し、その実現方法や応用について解説する。特に実現方法において重要な関数型暗号や暗号学的多重線形写像との関わりについても解説する。
2023年11月16日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
山内 卓也 氏 (東北大理)
超特殊アーベル多様体上の同種グラフ: 固有値, Bruhat-Tits ビルディングおよびProperty (T) (Japanese)
山内 卓也 氏 (東北大理)
超特殊アーベル多様体上の同種グラフ: 固有値, Bruhat-Tits ビルディングおよびProperty (T) (Japanese)
[ 講演概要 ]
正整数$g$, 素数$p$, $\ell$に対して, 標数$p$の有限体上の次元$g$をもつsuperspecial abelian varietiesであって$\ell$-marking が指定されたもの全体の成す類から有限向き付き正則グラフを構成することができる. 講演ではこのグラフに対するランダムウォーク行列の性質を対応するBruhat-Tits buildingsを解析することで調べることができることを説明する. また, $g=2$のとき, 保型形式, 保型表現論の観点からランダムウォーク行列の固有値に関して何が期待されるかも説明する. 本研究は東京大学の相川 勇輔 氏、京都大学の田中 亮吉 氏との共同研究である.
正整数$g$, 素数$p$, $\ell$に対して, 標数$p$の有限体上の次元$g$をもつsuperspecial abelian varietiesであって$\ell$-marking が指定されたもの全体の成す類から有限向き付き正則グラフを構成することができる. 講演ではこのグラフに対するランダムウォーク行列の性質を対応するBruhat-Tits buildingsを解析することで調べることができることを説明する. また, $g=2$のとき, 保型形式, 保型表現論の観点からランダムウォーク行列の固有値に関して何が期待されるかも説明する. 本研究は東京大学の相川 勇輔 氏、京都大学の田中 亮吉 氏との共同研究である.
2023年11月09日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
高島 克幸 氏 (早大教育)
同種写像暗号の数理 (Japanese)
高島 克幸 氏 (早大教育)
同種写像暗号の数理 (Japanese)
[ 講演概要 ]
耐量子計算機暗号の一つである同種写像暗号は,楕円曲線間の同種写像を使った鍵共有や署名方式であり,CGLハッシュ関数,SIDH鍵共有,SQIsign署名などが基本的な方式として知られてきた.また、種数1の楕円曲線だけでなく,種数2曲線同種写像暗号の研究も進んでいる.本講演では,まず,それらの概要を報告するとともに,種数2 Richelot同種写像グラフに関する桂利行氏との共同研究成果も簡単に紹介する.
2022年に,Castryck–Decruに始まる一連の研究によって「補助点情報」を巧みに使ったSIDH 鍵共有に対する多項式時間攻撃法が発表された.種数1同種写像暗号に対するこれらの攻撃法においても,高次元アーベル多様体の同種写像が基本的な役割を果たしている.本講演後半では,種数2 Richelot同種写像を使ったCastryck–Decruの攻撃法を紹介して,Robertの8次元アーベル多様体を使った攻撃法にも簡単に触れる予定である.
耐量子計算機暗号の一つである同種写像暗号は,楕円曲線間の同種写像を使った鍵共有や署名方式であり,CGLハッシュ関数,SIDH鍵共有,SQIsign署名などが基本的な方式として知られてきた.また、種数1の楕円曲線だけでなく,種数2曲線同種写像暗号の研究も進んでいる.本講演では,まず,それらの概要を報告するとともに,種数2 Richelot同種写像グラフに関する桂利行氏との共同研究成果も簡単に紹介する.
2022年に,Castryck–Decruに始まる一連の研究によって「補助点情報」を巧みに使ったSIDH 鍵共有に対する多項式時間攻撃法が発表された.種数1同種写像暗号に対するこれらの攻撃法においても,高次元アーベル多様体の同種写像が基本的な役割を果たしている.本講演後半では,種数2 Richelot同種写像を使ったCastryck–Decruの攻撃法を紹介して,Robertの8次元アーベル多様体を使った攻撃法にも簡単に触れる予定である.
2023年11月02日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
安田 雅哉 氏 (立教大学)
格子問題の求解アルゴリズムとその応用 (Japanese)
安田 雅哉 氏 (立教大学)
格子問題の求解アルゴリズムとその応用 (Japanese)
[ 講演概要 ]
本講演では、格子問題を解くための必須の技術であるLLLやBKZなどの
格子アルゴリズムを紹介する。また、LWEやNTRUの格子問題への適用
方法を説明すると共に、素因数分解問題への応用についても述べる。
本講演では、格子問題を解くための必須の技術であるLLLやBKZなどの
格子アルゴリズムを紹介する。また、LWEやNTRUの格子問題への適用
方法を説明すると共に、素因数分解問題への応用についても述べる。
2023年10月19日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
高島 克幸 氏 (早大教育)
格子暗号の数理 (Japanese)
高島 克幸 氏 (早大教育)
格子暗号の数理 (Japanese)
[ 講演概要 ]
本講演では,格子暗号の数理を紹介する.まず、格子上のフーリエ解析に基づくRegevの格子暗号構成フレームワークとそれに基づく具体的な構成法を順に概説する.そして,加群格子・イデアル格子といった特別な格子に基づく暗号構成の基礎付けを見た後に,時間が許せば、Cramerらによる近似Ideal-SVP 問題に対する多項式時間量子アルゴリズムを概説する.
本講演では,格子暗号の数理を紹介する.まず、格子上のフーリエ解析に基づくRegevの格子暗号構成フレームワークとそれに基づく具体的な構成法を順に概説する.そして,加群格子・イデアル格子といった特別な格子に基づく暗号構成の基礎付けを見た後に,時間が許せば、Cramerらによる近似Ideal-SVP 問題に対する多項式時間量子アルゴリズムを概説する.
2023年10月05日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号とブロックチェーン (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号とブロックチェーン (Japanese)
[ 講演概要 ]
ブロックチェーンは分散環境下で多人数により合意形成を行う方式であり、基本的な暗号機能を用いて実現される。本講演では、その基本的なコンセプトの解説を行うとともに、最近の動向についても紹介する。
ブロックチェーンは分散環境下で多人数により合意形成を行う方式であり、基本的な暗号機能を用いて実現される。本講演では、その基本的なコンセプトの解説を行うとともに、最近の動向についても紹介する。
2023年07月13日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
完全準同型暗号と関数型暗号 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
完全準同型暗号と関数型暗号 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の最終回
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の最終回
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年07月06日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号プロトコル (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号プロトコル (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の12回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の12回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年06月29日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
ゼロ知識証明 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
ゼロ知識証明 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の11回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の11回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年06月22日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
格子暗号 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
格子暗号 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の10回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の10回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年06月15日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
楕円曲線を用いた暗号 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
楕円曲線を用いた暗号 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の9回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の9回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年06月08日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
ディジタル署名の安全性と構成、証明 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
ディジタル署名の安全性と構成、証明 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の8回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
(6月1日(木)はセミナーがありません)
13回の講演の8回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
(6月1日(木)はセミナーがありません)
2023年05月25日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
公開鍵暗号の安全性と構成および証明(2) (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
公開鍵暗号の安全性と構成および証明(2) (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の7回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の7回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年05月18日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
公開鍵暗号の安全性と構成および証明(1) (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
公開鍵暗号の安全性と構成および証明(1) (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の6回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の6回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年05月11日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
共通鍵暗号と公開鍵暗号の安全性定義と証明 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
共通鍵暗号と公開鍵暗号の安全性定義と証明 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の5回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の5回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年04月27日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号理論の基礎II(一方向性関数、疑似乱数、疑似ランダム関数など) (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号理論の基礎II(一方向性関数、疑似乱数、疑似ランダム関数など) (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の4回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の4回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年04月20日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号理論の基礎(一方向性関数、疑似乱数、疑似ランダム関数など) (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号理論の基礎(一方向性関数、疑似乱数、疑似ランダム関数など) (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の3回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の3回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年04月13日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
認証と署名、暗号理論の基礎 (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
認証と署名、暗号理論の基礎 (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の講演の2回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の講演の2回目
暗号理論の現状と今後の進展について講義する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年04月06日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 128号室
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号の役割(秘密鍵暗号と公開鍵暗号) (Japanese)
岡本 龍明 氏 (NTT)
暗号の役割(秘密鍵暗号と公開鍵暗号) (Japanese)
[ 講演概要 ]
13回の暗号理論解説の1回目。
暗号理論の現状と今後の進展について講演する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
13回の暗号理論解説の1回目。
暗号理論の現状と今後の進展について講演する。基本的な暗号理論が現在のネットワークでどのように使われているかを理解するとともに、その安全性を証明する理論についても理解を深める。さらに、高度化した暗号や将来の計算機に対しても安全とされる暗号、ゼロ知識証明などの暗号プロトコル、暗号通貨やブロックチェーンなど、暗号理論の新しい進展や応用についても知見を得る。
2023年01月19日(木)
16:50-18:35 数理科学研究科棟(駒場) 123号室
成定 真太郎 氏 (KDDI総合研究所)
符号暗号とその求解アルゴリズム (Japanese)
成定 真太郎 氏 (KDDI総合研究所)
符号暗号とその求解アルゴリズム (Japanese)
[ 講演概要 ]
耐量子暗号の候補である符号暗号について紹介するとともに、符号暗号の解読アルゴリズムであるInformation Set Decoding (ISD)について解説する。また、ISDの量子アルゴリズムについて紹介する。
耐量子暗号の候補である符号暗号について紹介するとともに、符号暗号の解読アルゴリズムであるInformation Set Decoding (ISD)について解説する。また、ISDの量子アルゴリズムについて紹介する。
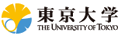
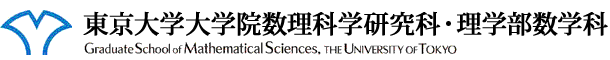
 本文印刷
本文印刷 全画面プリント
全画面プリント