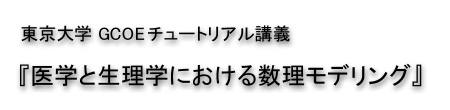
|

|
 日程: 2010年7月13日(火)〜14日(水) 日程: 2010年7月13日(火)〜14日(水)
| |||||||||
 場所: 東京大学大学院数理科学研究科棟大講義室 (京王井の頭線駒場東大前駅よりすぐ) 場所: 東京大学大学院数理科学研究科棟大講義室 (京王井の頭線駒場東大前駅よりすぐ)
| |||||||||
 講師(講演順): 講師(講演順):1. 岡田 康志 氏(東京大学医学系研究科 細胞生物学・解剖学教室) 2. 森 洋一朗 氏(ミネソタ大学 数学科) | |||||||||
 プログラム: プログラム:
|
1. 岡田 康志 氏:「アルツハイマーから心臓まで 〜分子モーターの多彩な機能とそのモデル化〜」
[第1部] 分子モーターの動きの機構とモデル化 〜アルツハイマーと交通渋滞〜
(キーワード:ブラウン運動,ラチェット機構,パロンドの逆理,交通流モデル)
[第2部] 左右軸決定の流体力学モデル 〜心臓が左側にある理由〜
(キーワード:ポワズイユ流,反応拡散方程式)
 概要:
《動くこと》は生命現象の大きな特徴の一つである.その源である分子モーターは,動くことを通じて多彩な生命現象に寄与している.
たとえば分子モーターのキネシンは、記憶・学習などの高次脳機能,アルツハイマーなどの神経疾患,さらには人体の左右非対称性(心臓が左側にあるなど)でも重要な役割を果たしている.
今回は,キネシン1個の動きから高次の現象まで,私自身の実験とそれを元にした数理モデルを中心に紹介する予定である。
概要:
《動くこと》は生命現象の大きな特徴の一つである.その源である分子モーターは,動くことを通じて多彩な生命現象に寄与している.
たとえば分子モーターのキネシンは、記憶・学習などの高次脳機能,アルツハイマーなどの神経疾患,さらには人体の左右非対称性(心臓が左側にあるなど)でも重要な役割を果たしている.
今回は,キネシン1個の動きから高次の現象まで,私自身の実験とそれを元にした数理モデルを中心に紹介する予定である。
2. 森 洋一朗 氏:「電気生理学における数理」
(1) 細胞の体積調節と膜電位の起源(イオンチャネル・ポンプ,浸透圧,電解質バランス)
(2) 活動電位と興奮性(Hodgkin-Huxley, FitzHugh-Nagumo モデル,dispersion relation)
(3) 心不整脈の理解をめざして(Bidomain モデル,スパイラル波,restitution hypothesis)
 概要:
神経系での情報処理から心臓のリズムの同期にいたるまで,我々の身体のさまざまな機能は電気的に制御されている.
前半では細胞の体積調節を起点として電気生理学の基礎的概念について数理モデルを通して解説する.
後半ではこのような数理モデルが心臓の不整脈の理解にどう貢献しつつあるのか解説する予定である.
概要:
神経系での情報処理から心臓のリズムの同期にいたるまで,我々の身体のさまざまな機能は電気的に制御されている.
前半では細胞の体積調節を起点として電気生理学の基礎的概念について数理モデルを通して解説する.
後半ではこのような数理モデルが心臓の不整脈の理解にどう貢献しつつあるのか解説する予定である.
 世話人: 俣野博,奈良光紀, 問い合わせ先: matano
世話人: 俣野博,奈良光紀, 問い合わせ先: matano ms.u-tokyo.ac.jp
ms.u-tokyo.ac.jp