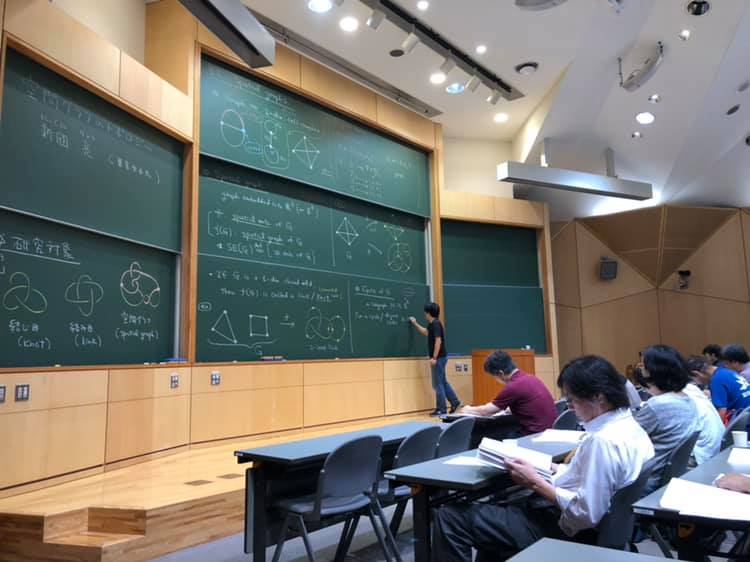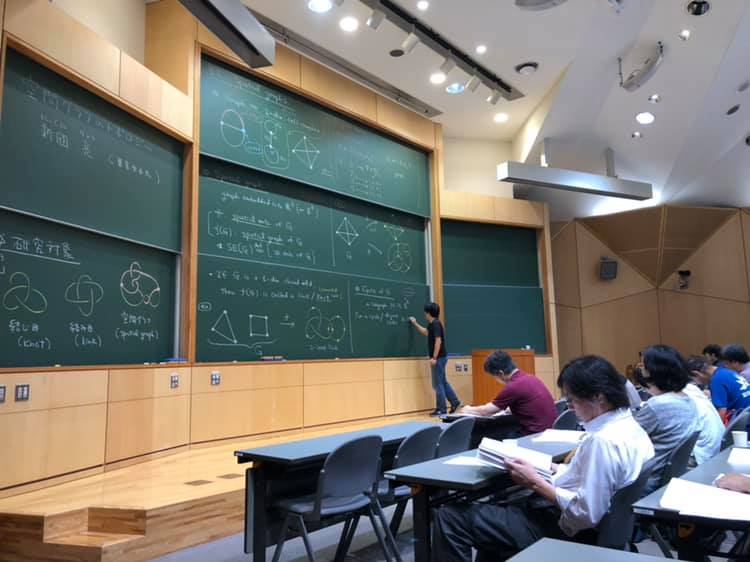Summer School 数理物理
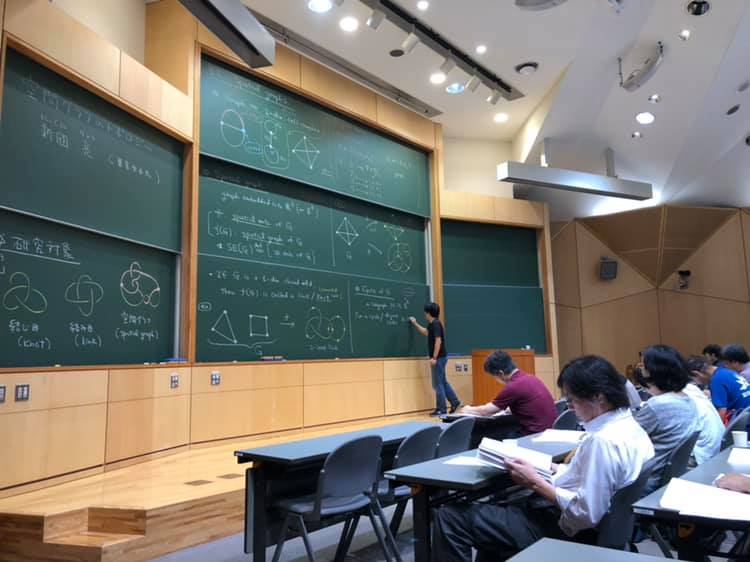
1987年から2001年まで,荒木不二洋先生と江沢洋先生の主催により,
学習院大学で行われていました.2002年より,小嶋と河東の
担当になり,現在は,緒方と河東の担当で行っています.
2025年の会場は京大数理研となりました.
「これから研究を始めようとしている院生や,数理物理の広い分野にわたる
(専門外の)研究者を対象とする入門的な講義」というのが趣旨です.
世話人:緒方芳子,河東泰之
1987 数理物理への誘い
| 吉川圭二 | 阪大・理・物理 |
String theory |
| 近藤慶一 | 名大・理・物理 |
Random walk methods |
| 土屋昭博 | 名大・理・数学 |
Conformal field theory |
| 谷島賢二 | 東大・教養・数学 |
Schrödinger operators
|
|
1988 共形場・量子群・可解模型
| 江口 徹 | 東大・理・物理 |
Conformal field theory |
| 野海正俊 | 上智大・理工・数学 | |
| 上野喜三雄 | 早大・理工・数学 | Quantum group |
| 中神祥臣 | 横浜市大・文理・数学 | |
| 河野俊丈 | 名大・教養・数学 |
Braid群とYang-Baxter方程式 |
| 国場敦夫 | 東大・教養・物理 | 可解格子模型
|
|
1989 径路積分と確率論
| 一瀬 孝 | 金沢大・理・数学 |
Path integral 入門 |
| 高橋陽一郎 | 東大・教養・数学 |
Large deviation and statistical mechanics |
| 田崎晴明 | 学習院大・理・物理 |
Roles of percolation in statistical mechanics |
| 黒田耕嗣 | 慶応大・理工・情報 |
確率論から見たスピン系の相転移 |
| 甘利俊一 | 東大・工・物工 | 神経回路網の数理
|
|
1991 微分幾何と物理
| 深谷賢治 | 東大・理・数学 |
Gauge場の数理 |
| 満渕俊樹 | 阪大・教養・数学 |
Einstein計量とmoduli空間 |
| 川合 光 | 東大・理・物理 | 2次元重力 |
| 細谷暁夫・樋口三郎 | 東工大・理・物理 |
Topology change in quantum gravity and hyperbolic 3-manifolds
|
|
1992 力学系
| 大森英樹 | 東京理大・理工・数学 |
幾何学的描像と非可換の世界 |
| 俣野 博 | 東大・数理 |
力学系の理論と非線形微分方程式 |
| 村井信行 | 中京大・教養・物理 |
拘束系の力学とホモロジー |
| 山田道夫 | 京大・防災研 | ウェーブレット解析
|
|
1993 カオスとフラクタル
| 楠岡成雄 | 東大・数理 |
フラクタル上の解析学 |
| 松下 貢 | 中大・理工・物理 |
フラクタル・パターン形成の物理 |
| 丹羽敏雄 | 津田塾大・数学 |
ハミルトン系とカオス |
| 山口昌哉 | 京大・理・数学 | カオスとフラクタル
|
|
1994 量子力学の基礎にある問題
| 新井朝雄 | 北大・理・数学 |
Aharonov-Bohm 効果 |
| 磯崎 洋 | 阪大・理・数学 |
量子力学的多体問題の数学的側面 |
| 小沢正直 | 名大・情報文化 |
観測の理論: 測定は対象をどう変化させるか? |
| 矢崎治一 | 兵庫教育大・物理 |
量子力学における位相と Gribov horizon
|
|
1995 無限可積分系と対称性
| 中西知樹 | 名大・多元数理 |
場の理論における Yangian 対称性 |
| 中屋敷厚 | 九大・数理 |
アフィン量子群の表現論と可解格子模型 |
| 栗田英資 | 京大・基研 |
多体問題の話題から -- McDonald 多項式をめぐって |
| 梁 成吉 | 筑波大・物理 |
2次元共形場理論の変形問題
|
|
1996 Fermat の最終定理
| 足立恒雄 | 早大・理工・情報 |
楕円曲線の数論とフェルマーの最終定理 |
| 田口雄一郎 | 都立大・理・数学 |
Fermat の最終定理 -- Wiles による証明の簡単な解説 |
| 寺杣友秀 | 東大・数理 |
関数体上の Langlands 予想について
|
|
1997 非可換幾何とその周辺
| 泉 正己 | 東大・数理 |
Superselection rules and subfactors |
| 森吉仁志 | 北大・理・数学 |
非可換幾何学と指数定理 |
| 森田克貞 | 名大・理・物理 |
非可換幾何とゲージ理論 |
| 新井朝雄 | 北大・理・数学 |
非単連結空間上のゲージ理論: 物理と表現論 --量子群および関連する側面--
|
|
1999 くりこみ群の方法
| 大野克嗣 | イリノイ大・物理 |
くりこみと漸近解析 --漸近解析は全てくりこみと解釈できるか |
| 渡辺 浩 | 日医大 |
場の理論の数学的構成におけるくりこみ群の方法 |
| 前島 信 | 慶応大・理工・数学 | 自己相似過程 |
| 青木健一 | 金沢大・理・物理 |
素粒子論における非摂動くりこみ群の最近の発展
|
|
2000 量子力学の数理 --加藤敏夫先生を偲んで
| 谷島賢二 | 東大・数理 |
Schrodinger 方程式の基本解 |
| 中村 周 | 東大・数理 |
相空間でのトンネル効果と散乱の半古典極限 |
| 廣島文生 | 摂南大・数学 |
量子化された輻射場と相互作用する原子のスペクトル解析: |
| | 汎関数積分によるアプローチ |
| 磯崎 洋 | 阪大・理・数学 |
スペクトル理論における逆問題
|
|
2001 非平衡統計力学の現在
| 田崎晴明 | 学習院大・理・物理 |
From quantum mechanics to second law of thermodynamics |
| 佐々真一 | 東大・総合文化 |
平衡と非平衡の熱力学II ミクロな動力学と定常状態熱力学 |
| 吉田伸生 | 京大・理・数学 |
Gibbs 分布と緩和現象 |
| 盛田健彦 | 広大・理・数学 |
Entropy, Lyapunov exponents, and Sinai-Bowen-Ruelle measures
|
|
| 江口 徹 | 東大・理・物理 |
超弦理論の現在 |
| 川合 光 | 京大・理・物理 |
行列模型による超弦理論の定式化と非可換幾何学 |
| 夏目利一 | 名古屋工大・数学 |
方向性のない不思議な世界:非可換幾何入門 |
| 綿村 哲 | 東北大・理・物理 |
非可換空間上のゲージ理論 |
| 有光敏彦 | 筑波大・物理 |
乱流のマルティフラクタル解析 |
| 小川知之 | 阪大・基礎工 |
周期波の弱非線形解析 |
| 木田重雄 | 核融合研 |
乱流の摂動理論 |
| 福本康秀 | 九大・数理 |
Euler-Poincaré 形式による渦のトポロジーと力学 |
| 粟田英資 | 名大・多元数理 |
頂点作用素の物理 |
| 山田裕理 | 一橋大 |
モンスター単純群と頂点作用素代数 |
| 吉荒 聡 | 東京女子大 |
最大位数の散在型単純群、モンスターの構造について |
| 脇本 実 | 九大・数理 |
W代数の話 〜 スーパー・コンフォーマル代数の表現論へ |
| 植田好道/日合文雄 | 九大・数理/東北大・情報 |
ランダム行列と自由確率論 |
| 種村秀紀 | 千葉大・理 |
ランダム行列と非交叉過程 |
| 永尾太郎 | 名大・多元数理 |
行列のブラウン運動と量子準位統計 |
| 中村勝弘 | 大阪市大・工 |
量子カオスの現在と未来 |
| 上田正仁 | 東工大・理工 |
冷却原子のボース・アインシュタイン凝縮 |
| 田崎晴明 | 学習院大・理 |
ボース・アインシュタイン凝縮の数理 |
| 小嶋 泉 | 京大・数理研 |
「量子古典対応」から見た「凝縮状態」とは? |
| 石田政司 | 上智大・理工 |
リッチフローと4次元異種微分構造 |
| 伊東恵一 | 摂南大・工 |
数理物理的(繰りこみ群の)視点からみたペレルマンの論文について |
| 小島定吉 | 東工大・情報理工 |
ポアンカレ予想と幾何化予想 |
| 小林亮一 | 名大・多元数理 |
非局所崩壊定理 -- 背景・証明・例 -- |
|
| 尾畑伸明 | 東北大・情報科学 |
量子確率論とグラフのスペクトル解析 |
| 香取眞理 | 中央大・理工 |
臨界現象・フラクタル曲線と Schramm-Loewner Evolution |
| 須鎗弘樹 | 千葉大・融合科学 |
Tsallis統計の基礎数理 |
| 長岡浩司 | 電通大・情報システム学 |
情報幾何から見たベキ乗構造 ---α接続の幾何 ---
|
|
| 大槻東巳 | 上智大・理工 |
ランダム媒質中を伝搬する波動の局在・非局在転移 |
| 小谷眞一 | 関西学院大・理工 |
1次元系の絶対連続スペクトルと可積分系 |
| 中野史彦 | 学習院大・理 |
アンダーソン局在と関連する話題 |
| 南 就将 | 慶応大・医 |
ランダム・シュレーディンガー作用素の基礎 |
|
| 井上 玲 | 千葉大・理 |
箱玉系の可積分性 --- クリスタルとトロピカル幾何 |
| 白石潤一 | 東大・数理 |
Ding-Iohara代数, Macdonald 関数とAGT予想 |
| 立川裕二 | 東大・IPMU |
4次元ゲージ理論と2次元共形場理論の不思議な関係 |
| 中西知樹 | 名大・多元数理 |
共形場理論と団代数 |
| 出口哲生 | お茶の水女子大・物理 |
ランダム結び目と環状高分子の統計物理 |
| 長尾健太郎 | 名大・多元数理 |
3次元双曲幾何とクラスター代数 |
| 藤 博之 | 名大・物理 |
結び目不変量と量子場の理論 |
| 村上 順 | 早稲田大・数学 |
結び目の量子不変量とその応用 |
| 新井朝雄 | 北大・数学 |
相対論的量子電磁力学の数理 |
| 河東泰之 | 東大・数理 |
共形場理論と作用素環 |
| 原 隆 | 九大・数理 |
構成的場の量子論 --- 古典的な問題の紹介 |
| 廣島文生 | 九大・数理 |
非相対論的量子場とギブス測度
|
|
| 佐藤昌利 | 名大・工 |
トポロジカル量子現象 ―トポロジカル超伝導体を中心に― |
| 玉木 大 | 信州大・理 |
トポロジカル相からK理論へ |
| 中野史彦 | 学習院大・理 |
量子ホール効果の数学的研究の現状 |
| 村上修一 | 東工大・理工 |
多様な粒子系におけるトポロジカル相
|
|
| Benoit Collins | 京大・数学 |
Entanglement and the area law |
| 高柳匡 | 京大・基研 |
ホログラフィー原理と量子エンタングルメント |
| 中山優 | Caltech |
局所繰り込み群とホログラフィー |
| 松枝宏明 | 仙台高専 |
場の量子論におけるテンソル積変分法 |
|
| 太田啓史 | 名古屋大・多元数理 |
Floer Theory and Mirror Symmetry |
| 高橋篤史 | 大阪大・理 |
超曲面特異点のミラー対称性と関連する話題 |
| 細野忍 | 学習院大・理 |
カラビ・ヤウ多様体の幾何学とミラーシンメトリー |
| 堀健太朗 | 東大・IPMU |
ミラー対称性講義
|
|
| 坂井哲 | 北大・理 |
有向パーコレーションの臨界現象:厳密な立場より |
| 佐野雅己・玉井敬一 | 東大・理 |
層流・乱流転移と普遍法則 |
| 竹内一将 | 東工大・理 |
吸収状態転移の物理学入門 |
| 米田剛 | 東大・数理 |
Pulsatile flowの乱流遷移とVortex breakdownに関する純粋数学的洞察の試み
|
|
| 塩崎謙 | 理研 |
対称性によって保護されたトポロジカル相における非局所秩序変数と位相的場の理論 |
| 村上順 | 早大・数学 |
Kontsevich 不変量,LMO 不変量と対応する位相的場の量子論 |
| 村上斉 | 東北大・情報 |
位相的場の理論に由来する3次元多様体の不変量(MOOとWRT) |
| 山崎雅人 | 東大・IPMU |
複素チャーン・サイモンズ理論 |
| 講演ビデオ | | |
| 河備浩司 | 慶応義塾大・経済 |
確率論から見た離散幾何解析入門 : 結晶格子の幾何学と中心極限定理 |
| 新國亮 | 東京女子大・現代教養 |
空間グラフのトポロジー 〜 外在的性質と内在的性質 |
| 見村万佐人 | 東北大・理・数学 |
離散群からエクスパンダーグラフを作る |
| 森岡悠 | 愛媛大・理工 |
格子上の離散シュレーディンガー作用素の連続スペクトル
|
|
| 古田幹雄 | 東大・数理 |
トーラス上のDirac作用素の正方格子による有限次元近似 |
| 松尾信一郎 | 名大・多元数理 |
Atiyah-Patodi-Singerの指数定理とドメインウォールフェルミオンの数学 |
| 山口哲 | 阪大・物理 |
フェルミオンの経路積分とAtiyah-Patodi-Singer 指数 |
| 米倉和也 | 東北大・物理 |
族の指数定理とフェルミオンのトポロジカル相の物理
|
|
| 瀧雅人 | 立教大学・人工知能科学 |
深層学習:その仕組みと応用と謎 |
| 田中章詞 | 理研・iTHEMS/AIP |
深層生成モデルの数理 |
| 持橋大地 | 統計数理研究所 |
ノンパラメトリックベイズ統計と統計的自然言語処理 |
| 森村哲郎 | サイバーエージェント |
強化学習 |
|
| 香取眞理 | 中央大・物理 |
ランダム行列・多重SLE・量子重力 |
| 佐々田槙子 | 東大・数理 |
箱玉系と確率論 -新たな出会いが古典を呼び起こす- |
| 笹本智弘 | 東工大・理 |
可積分確率論入門 -KPZ系を中心に- |
| 西成活裕・柳澤大地 | 東大・先端研 |
ASEPと渋滞学 |
|
2024 台風のため中止
| 天野一幸 | 群馬大学 情報学部 |
P vs. NP問題と回路計算量 |
| 河村彰星 | 京都大学 数理解析研究所 |
完全問題と「複雑さ」 |
| 西村治道 | 名古屋大学 情報文化学部 |
量子対話型証明 |
| 早川龍 | 京都大学 白眉センター/基礎物理学研究所 |
ハミルトニアン計算複雑性 |
|
河東のホームページに戻る.